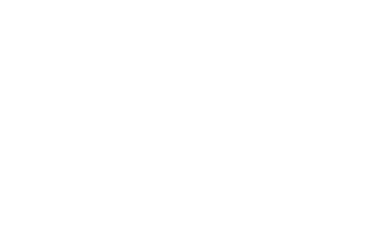PESO事例の詳細資料をダウンロードしませんか?
資料をダウンロードする
初心者でも簡単!カスタマージャーニーマップの作り方と活用法
マーケティング 2025.08.29

「カスタマージャーニーマップ」は、近年注目を集めているマーケティングの方法です。ビジネスにおいて重要性が高まっていますが、詳しいことをよく知らない方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、「カスタマージャーニーマップ」についてわかりやすく解説します。意味やメリット、注意点などを把握するのにお役立てください。
目次
カスタマージャーニーマップとは顧客の行動を可視化したもの
日本語にすると「顧客の旅の地図」となるカスタマージャーニーマップ。
わかりやすく言えば、「顧客が商品やサービスに出会い、実際に購買行動に至るまでのプロセスを可視化したもの」です。
広告でその商品の存在を知り、サイトやレビューを見て類似商品と比較し、購買するといった一連の流れを「旅」に例え、さらにそれを目に見える形で表したものを「地図」に例えています。
カスタマージャーニーマップは「課題が見えやすくなる上、アプローチ方法や改善策を考えやすい」として必要性を認め、作成する企業が増えています。
カスタマージャーニーマップの重要性
カスタマージャーニーマップは、顧客行動を可視化し、顧客との関係を深めるための重要なツールです。その必要性は、以下の理由から明らかです。
まず、デジタル接点の増加による顧客行動の複雑化があります。SNSや口コミサイト、公式ウェブサイトなど、顧客は多様なチャネルを行き来しながら意思決定を行います。このような複雑なプロセスを把握し、顧客のニーズを正確に理解するには、ジャーニーマップが欠かせません。
次に、社内の顧客理解を統一する役割があります。マーケティング、営業、カスタマーサクセスなどの部門間で認識が分断されることはよくありますが、ジャーニーマップを用いることで、顧客像や課題を共有し、施策の一貫性を保つことができます。
さらに、ジャーニーマップは戦略の基盤となります。例えば、PESO戦略やコンテンツマーケティングでは、顧客がどの段階で何を求めているかを理解することが成功の鍵です。ジャーニーマップは、こうした施策の方向性を明確にします。
最後に、顧客中心の視点を企業に定着させる効果もあります。顧客の体験を整理することで、CX(顧客体験)の改善を促し、真に求められる価値を提供することが可能になります。

カスタマージャーニーマップ作成の5つのメリット
カスタマージャーニーマップで顧客の行動や思考を可視化することには、大きく5つのメリットがあります。
- 顧客行動を全体像で把握し、課題を明確化できる
- 従来の手法では捉えにくい行動プロセスを可視化できる
- 部門横断で共通認識を形成できる
- 顧客視点に立った施策検討が可能になる
- 課題解決の優先度を整理・特定できる
それぞれについて、詳しく解説します。
顧客行動を全体像で把握し、課題を明確化できる
カスタマージャーニーマップを作る際は、顧客の行動や思考を洗い出し、情報を1枚のシートにまとめます。
情報を網羅的に検討するのに加え、全体像をわかりやすく俯瞰できるため、今まで気づかなかった課題を発見できる可能性が高まります。
従来の手法では捉えにくい行動プロセスを可視化できる
近年は、スマートフォンの普及やSNSの台頭で、顧客が商品やサービスに出会う機会が多様化しました。実店舗や企業による宣伝だけでなく、個人による発信でも、商品認知や実際の購買につながるようになっています。
そのため、従来のマーケティングのやり方では、顧客行動を把握しきれないという問題があります。
一方、さまざまな接触ポイント(タッチポイント)を検討するカスタマージャーニーマップでは、このような近年の傾向にも対応できます。
部門横断で共通認識を形成できる
カスタマージャーニーマップは一人で作るものではなく、関係者たちの協力が必要です。
各所から情報を集めて整理する中で、関係者全員が現在の状況を把握できるほか、課題に対する共通認識を持つことができます。
顧客視点に立った施策検討が可能になる
何か事業を進めようとするとき、どうしても企業目線から考えてしまい、「こうあってほしい」という希望的観測が含まれがちです。
しかし、カスタマージャーニーマップはあくまで「ユーザーの立場」から作ることから、顧客の考えに寄り添った進め方を検討できます。
課題解決の優先度を整理・特定できる
カスタマージャーニーマップは、顧客の行動フェーズごとに課題を見つけ、それを時系列順に整理します。
そのため、優先して対応するべき問題点が見つけやすくなります。
カスタマージャーニーマップの活用方法・施策
カスタマージャーニーマップは、顧客の行動や感情を深く理解し、各部門の施策を効果的に連携させるための重要なツールです。このカスタマージャーニーマップの具体的な活用法を解説します。
PESOモデルを使ったタッチポイント強化
カスタマージャーニーマップと、以下のPESOモデルを組み合わせることで、顧客との接点であるタッチポイントを強化できます。
- Paid(広告):新規認知やリード獲得を目的とした広告施策を展開します。例えば、Google広告やSNS広告を活用し、顧客の認知段階をサポートします。
- Earned(口コミ・メディア):メディア掲載や口コミを通じて信頼を醸成します。レビューサイトやユーザー生成コンテンツ(UGC)を活用することで、顧客の検討段階を支援します。
- Shared(SNS):SNSを通じて顧客との双方向コミュニケーションを図ります。顧客の質問に答えたり、コメントに反応したりすることで、より深い関係を構築します。
- Owned(自社メディア):自社ウェブサイトやブログ、メールマガジンなどで継続的に価値を提供します。購入後の顧客に対して役立つ情報を発信し、継続利用を促進します。
各フェーズに適したタッチポイントを設計することで、新規認知から継続利用に至るまで、顧客がどの接点に触れても、期待に応える体験を提供できる仕組みを構築できます。タッチポイントの設計がジャーニー全体で統一されることで、一貫性のあるブランド体験を実現し、顧客満足度の向上につながります。
PESO、および各メディアについては以下の記事で詳しく解説しています。
◆アーンドメディアとは?第三者メディアを活用した広報・PRの基本と活用法
◆オウンドメディアとは?作成する意味や作成方法、事例を一挙に解説
マーケティング施策との連動
カスタマージャーニーマップは、マーケティング施策を顧客の行動や感情に基づいて最適化するための基盤となります。マーケティング施策では、顧客の認知から購入、さらに継続利用に至るまで、それぞれのフェーズで異なるニーズに応える必要があります。ジャーニーマップを活用することで、顧客がどの段階にいるかを明確化し、施策をフェーズごとに適切に設計することが可能です。
以下はフェーズごとの施策例です。
- 認知フェーズ:ブランド紹介や問題提起に関するコンテンツを配信し、顧客が課題を認識できるようにします。
- 検討フェーズ:製品比較やケーススタディを提供して、顧客の意思決定をサポートします。
- 購入フェーズ:特典やキャンペーンを活用して、購入を後押しします。
- 継続フェーズ:顧客の満足度を高めるため、導入後の活用ガイドやフォローアップコンテンツを配信します。
なお、購入までのプロセスを図解したい場合、マーケティングファネルも有効です。マーケティングファネルを活用することで、消費者がどのフェーズで離脱しているのかを特定できるようになり、マーケティングの改善が可能になります。
マーケティングファネルについては「マーケティングファネルとは?意味や種類、活用されるシーンを解説」で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
営業・カスタマーサクセスとの連携
営業やカスタマーサクセス部門とジャーニーマップを共有することで、顧客の体験を最適化し、満足度を向上させることが可能です。具体的には、以下のような対応が可能になります。
- 商談や契約更新のタイミングでのアプローチ:ジャーニーマップを活用して顧客の状況を把握し、適切なタイミングで営業アプローチを行います。
- 導入後のサポートや教育コンテンツ:カスタマーサクセス部門は、導入後の顧客を支援するためのガイドやトレーニングを提供し、顧客が価値を最大限に享受できる環境を整えます。
- マーケティングデータの共有による効率化:マーケティング部門から得られる顧客データを営業やカスタマーサクセス部門と共有することで、施策の統合を図り、業務効率を向上させます。
これにより、各部門が連携して顧客体験を改善し、顧客との関係性を強化することができます。
カスタマージャーニーマップの作り方5ステップ
こちらでは、カスタマージャーニーマップを作る際の具体的な作り方を解説します。主な手順は以下のとおりです。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
1.ゴール(目標)設定
そもそも、カスタマージャーニーマップを作ることで得たい成果は何でしょうか?
売上30%アップなのか、資料請求件数の増加なのか、それとも顧客にSNSでシェアしてほしいのかなど、マップを作ることで目指したいゴール(目標)を明確にしましょう。
それによって、必要なデータや想定すべき顧客の行動も変わってきます。
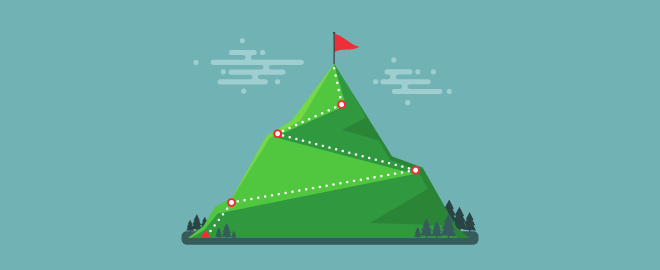
2.ターゲット(ペルソナ)設定
次に、事業の中心となるターゲットを決めます。佐藤
このとき、できるだけ具体的な人物像(ペルソナ)を設定することがおすすめです。性別や年齢、仕事、趣味、家族構成などまで考えるのが理想です。行動や感情を想定しやすくなるほか、関係者間での認識がブレにくくなるからです。
ペルソナ設定方法について詳しくは「ペルソナ設定のやり方決定版!項目から設定手順まで解説」をご覧ください。
3.フレームワーク(枠組み)を用意
カスタマージャーニーマップには、基本的なフレームワークがあります。
- 横軸は、「認知」「興味・関心」「比較検討」「行動」といったフェーズ(時系列順)
- 縦軸は、「接触ポイント(タッチポイント)」「感情・思考」「課題」「施策」などの情報
がよく見られる型です。インターネット上にはテンプレート例もありますので、うまく活用しましょう。
4.ペルソナの行動などを想定・調査
横軸に設定したフェーズに合わせ、ペルソナが実際に行うと予想される行動を調査します。
自分の頭だけで考えるのではなく、実際のユーザーにヒアリングしたり、アンケート調査を行なったりすると、より現実的なデータが手に入ります。
行動だけでなく、「顧客は何を考えるか?」「どんな不満を持つか?」といった思考面・感情面も想定することで、さらに説得力のあるカスタマージャーニーマップが作れます。
5.フレームワークに書き込み
情報が出揃ったところで、用意したフレームワークの中にそれらを書き込んでいきます。 文字だけでなく、イラストなどの図解も含めるとわかりやすくなります。
カスタマージャーニーマップ作りで注意すること
実際にカスタマージャーニーマップを作成する際、気をつけたいポイントもいくつかあります。実際にカスタマージャーニーマップ作りを行う場合には、以下の注意点を念頭に置いて作業してみてください。
マップ作成を目的化しない
カスタマージャーニーマップは、あくまで施策を効果的に実現し、ビジネスの目標を達成するためのものです。
マップの作成ばかりに注力し、手段が目的化しないように注意しましょう。
最初はシンプルなものを作る
特に初めてカスタマージャーニーマップを作る方は、シンプルなものを作成するのがおすすめです。
インターネット上で見つかる事例の中には、緻密に作り込まれて見栄えも良いマップもあるため、真似したくなるかもしれません。しかし、慣れない中で同じように複雑なマップを作ろうと思っても、完璧に作ることは難しいです。
最初は大まかに全体を作り、細かい部分は徐々に作り込んでいきましょう。
定期的に内容を更新する
現代は、新しい情報がすぐ陳腐化するような変化の激しい時代です。ユーザーの行動も、世の中に合わせてどんどん変わります。
マップは定期的に内容を更新し、顧客行動の変化に柔軟に対応できるようにしましょう。
カスタマージャーニーマップを活用してマーケティング施策の精度を向上させよう
カスタマージャーニーマップは、顧客の行動や感情を段階ごとに可視化したものであり、よりよいマーケティング施策を考えるのに役立ちます。
しかし、実際にマップを作成しようとしたとき、「思ったように作れない」「これで良いのかわからない」などの悩みが出てくるかもしれません。
パンタグラフでは、カスタマージャーニーマップ作成支援を行なっています。詳しいヒアリングやデータ分析を通して、ペルソナの購買行動につなげるための最適なマップ作りをサポートします。
無料でご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
関連する記事
pagetop