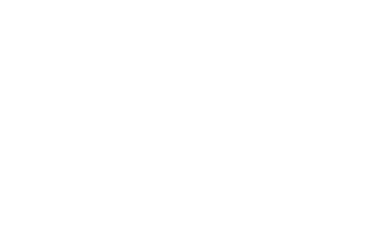PESO事例の詳細資料をダウンロードしませんか?
資料をダウンロードする
シェアードメディアとは?特徴や活用事例について解説
マーケティング 2025.03.18

シェアードメディアとは、SNSや口コミサイトなどを通じてユーザーが主体的に情報を共有・拡散するメディアのことです。SNSの著しい発展により、企業の認知拡大やブランディングにおいて重要な役割を担っています。
本記事では、シェアードメディアの特徴やメリット・デメリット、活用例などを解説します。SNSを活用したマーケティング戦略に興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
シェアードメディアとは
「シェアードメディア(Shared Media)は、オウンドメディア・ペイドメディア・アーンドメディアと並び、Webマーケティングの主要なメディアの一つです。具体的には、FacebookやX、InstagramなどのSNSや、食べログ、ホットペッパーグルメなどの口コミサイトが挙げられます。
これらのメディアで、主にコンテンツを発信するのは、企業ではなく消費者であることが大きな特徴です。消費者がシェア機能を活用して、企業や商品、サービスに関する情報を投稿・拡散することで、ブランドの認知拡大やイメージ向上に寄与します。
なお、オウンドメディア・ペイドメディア・アーンドメディア・シェアードメディアを総合的に活用するWebマーケティング戦略は、それぞれの頭文字をとって「PESOモデル」と呼ばれます。各メディアの特性を活かしながら組み合わせることで、より多角的なアプローチが可能です。
PESOモデルについて詳しく知りたい方は「PESOモデルとは?デジタル時代の集客戦略を解説」の記事もご覧ください。
シェアードメディアのメリット
シェアードメディアは、次のようなメリットがあります。
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
ノーコストで情報拡散が可能
シェアードメディアは、コストをかけずに情報を拡散できる点が大きなメリットです。広告会社を利用する場合は多額の費用が発生しますが、SNSの導入は基本的に無料であり、消費者が自発的に投稿・拡散するため、広告費をかけずに広範囲に情報を届けられます。
広告費用が限られている中小企業や個人経営の店舗にとっても、費用対効果の高いマーケティングツールとして重宝されています。実際に、小さな飲食店が1枚の写真をきっかけにSNSで話題になり、売上が急増するケースも少なくありません。

リアルタイムでユーザーの反応がわかる
シェアードメディアは、リアルタイムでユーザーの反応を把握できることもメリットの一つです。SNSでは、ユーザーが投稿した内容に対して「いいね」やコメントがつき、リポストの数なども即座に確認できます。さらに、「⚪︎分前に反応がありました」といった通知が届くプラットフォームもあるため、消費者の興味や関心、反応を迅速に分析することが可能です。
また、コメントやリポストでは、具体的な意見や感想が見られるため、反応に応じてマーケティング戦略の修正やサービス内容の改善を検討できます。たとえば、新商品のプロモーションで反響が大きければ追加の情報発信を行い、逆に反応が薄ければ内容をブラッシュアップしてアプローチ方法を変えるなどの対策を行います。
消費者のレビューで集客や売上の向上が見込める
消費者のリアルな体験談は、情報の信頼性が高く、集客や売上の増加が期待できる点がメリットです。特に、SNSやブログで発信される内容は、潜在顧客の興味を強く引きつけ、購買意欲を刺激しやすい傾向があります。良いレビューや評価が広がることでブランドのイメージや信頼性が向上し、新たな顧客の獲得にもつながる点も利点です。
企業側は、商品やサービスのリアルな評価を得て、商品開発やマーケティング戦略の改善に役立てられます。さらに、積極的にユーザーの投稿をシェアしたり、レビューを活用したマーケティングを行ったりすることで、集客効果がさらに向上します。

シェアードメディアのデメリット
シェアードメディアには多くのメリットがある一方で、次のようなデメリットも存在します。
- 情報コントロールが難しい
- 事実とは異なる内容が拡散される可能性がある
シェアードメディアの発信内容は消費者に委ねられるため、企業側がコントロールすることは困難です。必ずしも好意的な口コミばかりが拡散されるとは限らず、批判や否定的な意見が広まると、企業のイメージダウンや炎上につながるリスクがあります。
また、根拠のないうわさや間違った情報が広がるリスクも懸念点の一つです。特に、情報が瞬時に拡散されるSNSでは、企業が対策を講じる間もなく、たった一つの投稿が大きな影響を与えることも少なくありません。
これらのリスクを最小限に抑えるためには、次のような対策があります。
- 公式サイトやSNSで定期的に正しい情報を発信し、誤解を未然に防ぐ
- ネガティブな投稿に対して適切な説明や改善策を提示し、信頼性を高める
- 誤った情報が拡散された場合は迅速に正しい情報を発信し、誤情報の修正を図る
- カスタマーサポートを充実させ、疑問や不安を解消できる体制を整える

シェアードメディアの種類と活用法
シェアードメディアを効果的に活用するためには、それぞれのプラットフォームの特性を理解し、適切な戦略を立てることが大切です。ここからは、代表的なプラットホームの特性や活用方法を紹介します。
Facebook:シェアボタンでユーザーに直接共有できる
Facebookは、世界的に利用されているSNSです。シェアボタンの他に、共通の関心を持つ方が交流できる「Facebookグループ」機能があります。これを活用することで、グループ内で情報を一斉に共有し、長期的なエンゲージメントの向上が見込めます。
また、アカウントの作成時に実名登録が必須であるため、他のSNSと比較して信頼性が高いことも特徴です。企業はビジネス用ページを作成でき、ペイドメディアとしても活用できます。
さらに、他のSNSと比較すると長文の投稿が多い傾向です。テキスト、画像、動画、リンクを自由に組み合わせられるため、商品ページへの誘導もスムーズに行えます。
しかし、拡散力は他のSNSに比べてやや控えめです。信頼性やエンゲージメントを重視したプラットフォームであるため、短期間での拡散を狙うよりも、ファンの育成や長期的な関係構築に適しています。
X:リポストで簡単に情報を拡散できる
Xは、最大140字までの短い文章や画像、動画の共有ができます。「リポスト」と呼ばれる拡散機能があり、SNSの中でも情報拡散力が非常に高い点が最大の特徴です。さらに、リポスト数や閲覧数が数字で表示されるため、拡散規模を一目で把握できます。
なお、Xは利用者の年齢層が広く、幅広い年代をターゲットにした商品やサービスの認知拡大に適しています。さらに、トレンド機能を活用し、流行している話題に関連した投稿を行うことで、短期間で高いリーチと注目を集めることが可能です。
一方で非常に拡散力が高いため、ネガティブな情報も一気に広がるリスクがある点に注意が必要です。企業がXを活用する際は、炎上や誤った情報の拡散に対する対応策を事前に考えておくなど、慎重な戦略が求められます。

Instagram:写真や動画メインで製品を紹介できる
Instagramの投稿は写真や動画など、視覚的なコンテンツをメインとしたSNSです。特に、トレンドに敏感な20代の利用率が高い傾向にあり、魅力的なビジュアルを使って商品紹介すると、拡散力がさらに向上します。
また、投稿に商品タグをつけることで、商品名や価格などの商品情報の表示や自社のECサイトへの遷移が可能です。消費者は、商品の認知から購入までをワンステップで行うことができ、購買行動が促進されます。
さらに、ライブ配信機能も搭載されており、配信中にユーザーとコメントを通してコミュニケーションを取ることも可能です。ライブ配信でのリアルタイムのコメントのやり取りや、日常を気軽に投稿できる「ストーリーズ」機能は、企業とユーザーの距離感を縮めるのに適しています。
インスタグラムは若年層をターゲットに、視覚的な魅力や親しみやすさを活かした広告や宣伝が非常に効果的なプラットフォームだといえます。
YouTube:動画で伝えたい情報を存分に紹介できる
YouTubeは、動画をメインとした世界最大の動画共有プラットフォームです。動画にはコメントを入れることもでき、商品やサービスのチュートリアル、使い心地、機能性などを視覚的に紹介できます。また、ライブ配信機能を活用して、視聴者とリアルタイムで交流を深められることも魅力です。
しかし、YouTubeは競争が激しく、戦略的なマーケティングが求められます。たとえば、適切なキーワードを動画のタイトルや説明に含めることで、ユーチューブ内検索やGoogle検索で上位表示されやすくなります。また、視聴者の関心を惹きつけるためには、コンテンツの質や更新頻度にも熟考が必要です。
なお、広告は、YouTubeが定める基準を満たすチャンネル登録者数の多いYouTuberの動画に表示されます。広告の種類はディスプレイ広告やバンパー広告などさまざまな形式があり、ターゲット層に合わせた形式を選択することが重要です。
TikTok:Z世代をターゲットにした広告に最適
TikTokのコンテンツは、15秒〜1分程度の短い動画がメインです。Instagramのリール動画やYouTubeのショート動画のような機能が搭載されており、印象的な音楽やエフェクトを駆使したコンテンツが多く投稿されています。特に、Z世代を中心に世界中で利用されており、人気が急速に加速している中国発のSNSです。
TikTokでの拡散がきっかけで爆発的に売れることを意味する「TikTok売れ」という言葉も生まれ、企業にとって非常に重要なマーケティングツールとして注目されています。
国内最大手の広告代理店として知られる電通では、「TikTok売れ」の事例には共通のフローがあることを発見しました。具体的には、生活者のターゲットインサイト(潜在的な欲求)をうまくつかみ、ポジティブな驚きをもたらすことで動画が拡散され、その結果商品やサービスが「世の中ごと」となることを明らかにしています。
つまり、TikTokで話題になった商品やサービスは、その他のプラットフォームでも共有され、商品の認知度を急速に高めるのです。
TikTokのマーケティング戦略のポイントは、印象的なコンテンツでターゲットの関心を引き、共感を呼び起こすことです。さらに、UGC(ユーザー生成コンテンツ)やクリエイターとのコラボが話題を後押しし、拡散力を最大化します。

シェアードメディアの特徴をおさえてマーケティング戦略に活かそう
シェアードメディアとは、FacebookやX、Instagramなど、ユーザーが自発的にコンテンツを投稿・共有するメディアのことです。コストをかけずに商品やサービスの認知拡大を図れることが最大のメリットで、広告予算が少ない企業でも取り入れられます。しかし、発信される内容を企業側がコントロールできません。
また、プラットフォームによって特性や利用者層などが異なるため、目的に応じて適切に使い分けることが重要です。
パンタグラフではお客様がどのような状況で何をすべきか、Webサービス全体の状況を見た上で、適切なアドバイスを実施しています。
本ページよりダウンロードできる資料には、詳しい導入事例や、サービス内容が記載されているので、ぜひご覧ください。 また、シェアードメディアに限らず、集客戦略全般ご相談も随時お待ちしております。ぜひお気軽にお問い合わせください!
関連する記事
pagetop