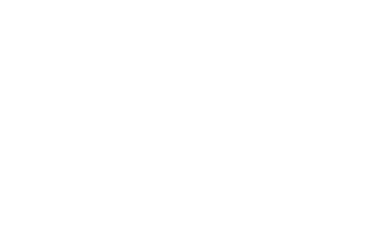パンタグラフ オリジナル資料
ヒューリスティック分析詳細資料無料配布中!
資料ダウンロードはこちら
【2025年版】IT・Webトレンドキーワード5選!意味や概要を解説
その他 2025.01.01

2024年はテクノロジーの飛躍的な進化が話題になりました。特にAI技術は進化と実用化が加速し、単純なタスクの自動化だけでなく、複雑な問題解決や意思決定の支援においても活躍するようになりました。
2025年においても、このようなテクノロジーの進化・革新は加速することが予想されます。
そこで本記事では、パンタグラフの独自目線で選んだ2025年のIT・Webトレンドのキーワード「偽情報セキュリティ」「インクルーシブデザイン」「AGI」「2025年の崖」「電動モペット」についてご紹介します。
目次
偽情報セキュリティ
2025年は、偽情報セキュリティがこれまで以上に重要になるでしょう。
偽情報セキュリティとは、偽情報や誤った情報から、人や組織、社会を守るための取り組みを指します。AI技術の進化によって偽情報が容易に生成されるようになった現在、偽情報が経済的な損失や、社会の分断を引き起こす危険性が高まり続けています。
このような危険性に対するため、2024年10月に、偽情報の検知から真偽の判定までを総合的に行うシステムの開発が決定しました。
この開発には、富士通やNECなどの大手メーカーと、慶應義塾大学や国立情報学研究所などの参加が予定されています。
それぞれが研究開発していた技術を統合し、2025年度末までに、偽情報の検知から根拠収集、分析、評価までを統合的に行う世界初の偽情報対策プラットフォームの構築が進められます。

偽情報と類語の定義
偽情報と似た言葉に誤情報やフェイクニュースがあります。また、諸外国では偽情報をDis-information(ディスインフォメーション)と呼び、さらに悪意のある情報をMal-information(マルインフォメーション)と呼びます。
それぞれの定義を確認しておきましょう。
- 偽情報(Dis-information)
受け取り手を誤解させるために意図的に作成された誤った情報、操作された情報
(虚偽の内容、捏造、なりすましなど)
- 誤情報(Mis-information)
間違っているが、発信者には悪意(意図)のない情報
(純粋な誤解など)
- 悪意のある情報(Mal-information)
事実に基づいた情報を悪用し、悪意(意図)を持って発信する情報
(リーク、ハラスメント、ヘイトスピーチの一部など) - フェイクニュース
明確な定義はありませんが、上記3つの偽情報・誤情報・悪意のある情報を総じて使われる場合が多いです。マスメディアを揶揄する目的でも使われます。

過去に拡散された偽情報の例
過去に拡散され、社会に影響を与えた偽情報には以下のような例があります。
災害時にライオンが動物園から逃走
2016年に熊本地震が発生した際、「動物園からライオンが逃げた」という虚偽の情報が画像付きでTwitter(現X)に投稿されました。
この偽情報により、熊本市動植物園には問い合わせの電話が殺到し、業務が妨害されました。なお、偽情報を投稿した人物は、偽計業務妨害の疑いで逮捕されています。
新型コロナウイルス拡散の影響でトイレットペーパーがなくなる
新型コロナウイルス拡散の影響でトイレットペーパーがなくなるという偽情報がSNS上で拡散されました。
マスクとトイレットペーパーの原材料が同じなので、マスクの増産に伴ってトイレットペーパーが不足するといった説明や、中国でトイレットペーパーの生産が止まる、あるいは原材料を中国から輸入できなくなることから日本国内で品不足になるといった説明があげられていました。
実際にはトイレットペーパーの約98%が国内で生産されており、原材料の調達も中国に依存していないにもかかわらず、結果としてトイレットペーパーの買いだめ騒動につながりました。
日本の海産物や化粧品は放射能の影響を受けている
2011年の東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故後、放射能汚染に対する不安が広がり、日本の海産物や化粧品は放射能の影響を受けているという偽情報がSNSなどで拡散されました。
実際には、水産庁や国際原子力機関(IAEA)などの調査によって、処理水の放出が人や環境に与える影響は「無視できる程度」だと結論づけられています。
また、過去に拡散された誤情報には以下のような例があります。
全く無関係の人物を犯人としてSNSで拡散
2019年に起きた茨城県の高速道路でのあおり運転事件で、無関係の女性が共犯の「ガラケー女」として誤って特定され、SNS上で晒されました。この誤情報により、女性のところには迷惑電話や誹謗中傷のメッセージが殺到しました。
女性は誤情報を拡散した愛知県の元豊田市議やユーチューバーを相手取り、裁判を起こしました。ユーチューバーとの裁判は続いていますが、元市議との裁判には勝訴しています。
戸籍の性別を性自認のみで変更できるという最高裁の判決
最高裁の判決が誤って解釈され、戸籍の性別を性自認のみで変更できるという判決がなされたとSNSで拡散されました。
最高裁は性同一性障害特例法についての裁判で、生殖不能要件(生殖腺を除去する手術を義務付けること)は違憲であると判断しました。しかし、外観に関する要件については高裁に審理を差し戻しており、性別変更の手続きには依然として複数の要件を満たす必要があります。
インクルーシブデザイン
インクルーシブデザインとは、多様性を尊重し、これまで製品やサービスのユーザーとして除外されてきた人々(高齢者・障がい者・外国人など)を企画の初期段階から巻き込んで考えていくデザイン方法です。Web、施設、ビジネスプロセスなど、幅広いジャンルで活用が進んでいます。
インクルーシブデザインによってより多くの人々が製品やサービスを利用できるようになり、社会全体の包摂性(インクルージョン)が高まることが期待されています。

インクルーシブデザインとユニバーサルデザインの違い
インクルーシブデザインは、よく比較・混同されるユニバーサルデザインと大きな目的は同じですが、ターゲットやアプローチが異なります。
ユニバーサルデザインは、状況や能力に関わらず、「できるだけ多くの人」をターゲットとして設定し、できるだけ多くの人が利用できる汎用的なデザインを、デザイナーが考案します。
一方、インクルーシブデザインは、年齢、身体的な特徴や障害、言葉の違いなど、特定の制約のある利用者を明確なターゲットに設定し、ターゲットとなる人と共に意見を交換しながらデザインを創造します。そのため万人向けのデザインにならないこともありますが、特定のニーズに応えることでより広い層に役立つ製品やサービスが生まれることもあります。

インクルーシブデザインの活用事例
インクルーシブデザインを取り入れた企業の活用事例を3つ紹介します。
マイクロソフト:デバイス「Xbox Adaptive Controller」「Adaptive Mouse」
マイクロソフトは様々な視点を持つ人を受け入れて製品開発を行う研究施設「インクルーシブ・テク・ラボ」を2017年に開設しました。
2018年に発表した「Xbox Adaptive Controller(エックスボックス アダプティブ コントローラー)」は、障がいのある人でも快適にゲームをプレーできるように開発されたコントローラーです。コントローラーに搭載されたポートにスイッチ・ボタン・ジョイスティックなどの外部デバイスを接続することで、一人ひとりの身体上の特徴に適したカスタマイズが可能です。
また2022年には、障がい者が、自分の障がいの程度にあった形・使い心地を選べるよう様々にデザインされたマウス「Adaptive Mouse(アダプティブ マウス)」を発表しました。
このマウスはアクセサリを追加したり、3Dプリントで作成したカスタム部品を使用したりすることで、ユーザーの身体的な状況に合った形状に調整できます。
ナイキ:シューズ「ゴーフライイーズ」
ナイキは、手を使わなくても着脱しやすい形状のハンズフリーシューズ「ゴー フライイーズ」を2021年に発売しました。
このシューズは開口部に足を入れるとロックされ、かかとのスタンドを踏めば解除されるという仕組みになっており、脱ぎ履きに時間や手間がかからない便利さがお年寄りや妊婦さんなどにも幅広く受け入れられています。
こちらは、脳性麻痺の少年の「靴紐を結ぶ心配をせずに大学に通いたい」というメールをきっかけにナイキとその少年とで開発されたものでしたが、特定のニーズに応えることでより広い層に役立つ製品やサービスが生まれた良い例といえるでしょう。
花王:洗剤「アタックゼロボトル」
花王は2019年に「アタックゼロボトル」を発売しました。こちらは視覚障害者や軽度のまひを持つ方などの協力を得て開発されたものです。1回のプッシュで5gを計量できる「ワンハンドプッシュ」が特徴で、片手で簡単に計量できるようになっています。
視覚障害の方や軽度のまひを持つ方のほか、握力の弱くなった高齢者などにも使いやすいインクルーシブデザインになっています。
AGI(汎用人工知能)
AGIはArtificial General Intelligence(汎用人工知能)の略で、人間のような汎用的な知能を持つ人工知能を指します。AGIは、人間のように広範なタスクを理解し遂行する能力を持つAIとして、その実現を期待されています。
AGI実現は2年から数年(2026年以降)と予測する意見が多い中、2024年11月に、OpenAIのCEO・Sam Altman氏は「2025年にAGIが来る」と発言しました。最も早い時期予測であることや、その発言者がOpenAIのCEOであることなどを理由に注目が集まっています。
また、ソフトバンクの孫正義氏やイーロン・マスク氏もAGIの実現時期について発言していますが、10年以内といった予測から数年以内という予測に前倒しし続けています。

AGIのメリット・デメリット
ここからは、AGIのメリットとデメリットを紹介します。
AGIのメリット
AGIのメリットの一つは、事前の機械学習がなくても、AIが人間と同じように様々な問題を解決できるようになることです。
例えば、現時点では、画像認識と生成のトレーニングを受けたAI モデルが、Web サイトの構築をすることはできません。これは「Webサイトの構築を事前学習していないから」というのが理由です
しかし、AGIは人間のような知能と自己学習能力を備えているため、既存の知識を応用し、あるいは人間の介入なしに自律的に学習を進めることで、事前学習が行われていないタスクでも実行できるようになります。
また、現在の生成AI以上のサポートを実現してくれることもメリットです。医療分野では病気の診断や新薬の開発、研究分野では膨大なデータの正確な分析、新しい理論や開発方法の提案、教育分野では生徒一人ひとりに合わせたカスタマイズ指導など、多岐にわたる分野で活躍することが期待されています。
>AGIのデメリット
AGIのデメリットの一つは複雑な法整備を進める必要があるという点です。AGIの実現・普及は、データプライバシーの保護、知的財産権の管理、労働法の見直しなど広範囲に影響があります。急速な技術の発展に法整備が追い付かない可能性や、国際的な法整備の進捗状況に格差が生まれる可能性もあるため、法整備の困難さはデメリットの一つといえるでしょう。
また、失業や職種の変化が生じることもデメリットとして考えられます。AGIによって多くの仕事が自動化された場合、AGIに仕事を奪われる人が大量に発生する可能性があります。またAGIが主なタスク処理を担当するようになることで、それを管理・調整する職種が増えるといった変化が予想されます。
そういった変化に対応できる人とできない人とでの格差が生じるリスクもあり、AGIの影響を受けた人への社会保障も検討する必要があるでしょう。
AI分野の進化速度は人間の適応速度を上回る可能性があるため、法整備や社会保障など、様々な課題に早急に対応することが求められます。

自律的にタスクを実行するAgentic AIにも注目
OpenAIが社内向けに発表した「AGIに至る5段階のロードマップ」のレベル3に位置する「Agentic AI(エージェンティックAI)」にも注目が集まっています。
OpenAIは、Agentic AIシステムを「あらかじめ行動を指定しなくても、長期にわたり一貫して目標達成に貢献する行動がとれることが特徴」と定義づけています。これは、現在の生成AIやエージェント型AIとは異なる高レベルのAIシステムです。
ChatGPTやGeminiなどのようなコンテンツを生成するのが目的の生成AIや、自動応答型チャットボットなどのような、特定のタスクや目標達成を目的としたエージェント型AIは現在でも存在します。
特に、エージェント型AIは、事前に設定した環境やデータを基に、目標達成に向けたタスク処理をある程度自律的に実行するプログラムです。しかし、これらのAIは前提として人間が指示を出す必要があります。
ところが、次のステップのAIシステムであるAgentic AIは、指示を出さずとも予期せぬ環境に適応し、複雑な目標を達成するために行動できるとされています。Agentic AIが実現した場合、その衝撃はこれまでのどのAIシステムよりも大きいかもしれません。
2025年の崖
「DXを推進しないと2025年から年間で現在の約3倍、約12兆円もの経済損失が発生する」という経済産業省の予測を「2025年の崖」と呼びます。「2025年の崖」という言葉は、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」と呼ばれる資料の中で初めて使用されました。
DXとはデジタルトランスフォーメーションの略語です。経済産業省は、DXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。
DXレポートでは「DXを推進しなければ業務効率・競争力の低下は避けられないため、日本国内の企業が市場で勝ち抜くためにはDXの推進が必要不可欠」としており、2025年の崖の影響は政府や企業のみで収まらず、一般市民にも及ぶと考えられています。

2025年の崖の課題
2025年の崖には、システム・人材・経営意識の3つの面で大きな課題があります。
- システムのレガシーシステム化
多くの企業のシステムがレガシーシステム化しています。レガシーシステムとは、古い技術や仕組みで構築された時代遅れのシステムを指します。
多くの企業のシステムは老朽化しており、度重なる改修でシステムが複雑化・ブラックボックス化しています。このレガシーシステム化によって、維持管理に多大なコストがかかり、新技術への対応が遅れ、柔軟に事業戦略を構築することが難しくなります。
また、システム開発をベンダー企業に任せている企業も多く、自社でのDX推進が難しいケースもあります。
- 人材不足
2025年に、従来のレガシーシステムを担う人材が定年を迎え、退職・高齢化します。
レガシーシステムはCOBOLという古いプログラミング言語で書かれていることが多く、COBOLがわかる第一線でシステムを守ってきた人材が大きく不足するようになると懸念されています。人材不足はシステムの刷新を阻み、かつシステムの維持や新システムの導入を難しくします。
また、DXは単なる技術導入ではなく、組織文化や働き方の変革も伴うため、IT人材だけでなく社内システムに精通した人材やプロジェクトマネジメントできる人材も必要とされています。
- 経営層の意識や理解
上述のDXレポートでは、DX推進に対する経営層の認識不足も大きな課題とされていました。多くの経営層が、レガシーシステム化がビジネスに与える影響を十分に理解しておらず、適切な対策ができていないというのが現状です。
経営陣の危機意識が薄いとレガシーシステムを改修しながら利用を続けることになり、維持管理に多大なコストがかかり続けてしまいます。DX推進のためには、経営層がその意義や必要性を深く理解し、具体的な経営戦略を立てていくことが必要となります。

2025年の崖を乗り越えるには
2025年の崖を乗り越えるためには、上述の課題を解決していくことが求められます。既存のレガシーシステムを最新のデジタル技術に対応したものへ刷新し、人材不足を解消し、DX推進への意識を高めます。
この取り組みは影響範囲が広く、一朝一夕で課題を解決するのは難しいため、計画的に実施する必要があります。自社内の問題、課題を抽出し、それを解決するための具体的な手段を導き出し、計画的かつ段階的に取り込むことが重要です。
電動モペット(フル電動自転車)
電動モペットとは、モーターとペダルがついた二輪車のことです。ペダルがありますが、ペダルを漕がなくても電動機能だけで走行できる原動機付自転車(原付)で、フル電動自転車とも呼ばれます。
市場縮小や排ガス規制強化などの影響で、国内メーカーのホンダ・スズキが原付バイクの国内生産を終える見通しである中、電動モペットは代用品になるのかと注目を集めています。
見た目は自転車ですが、電動アシスト自転車を含む一般的な自転車とは異なる「電動バイク」であり、2024年11月に施行された改正道路交通法にて、原付バイクと同じ扱いにすることが明文化されています。

電動モペットの規定
電動モペットは一般の自転車と違って原付バイクであるため、以下の要件を満たさなければならないと規定されています。
- 運転免許の取得と走行時の携帯
- ナンバープレートの取り付けと表示
- 自賠責保険または共済への加入
- 一般原動機付自転車の交通ルールの厳守
- 保安基準を満たす装置の装着
※保安基準を満たす装置とは、ヘッドランプ・テールランプ・ブレーキランプ・ウインカー・クラクション・バックミラーなどが挙げられます。
※特例特定小型原動機付自転車の要件(最高速度表示灯を点滅させている、6km/hを超える速度を出すことができないなど)を満たす場合、免許は不要となり、歩道の走行が可能となります。
電動モペットは原付バイクと比べて価格が高く、1回の充電で走行できる距離が短いなどの課題がありますが、オートバイを製造するホンダ、ヤマハ発動機、スズキ、川崎重工業の4社は、コスト削減に向けて電池規格の統一を決定しています。
カーボンニュートラルや排ガス規制への対応が求められる中、電動モペットは充電したバッテリーで駆動するためガソリンが不要であり、電気自動車と同様に排出ガスが無く、また騒音も少ないことから、環境に優しい移動手段として期待されています。
まとめ
本記事では、2025年のIT・Webトレンドの核となる以下の5つのキーワードをご紹介しました。
- 偽情報セキュリティ
- AGI(汎用人口知能)
- インクルーシブデザイン
- 2025年の崖
- 電動モペット(フル電動自転車)
これらのトレンドは、私たちの生活やビジネスに新たな変革をもたらすと予想されます。紹介したキーワードに関する情報への理解を深めて、2025年以降のIT・Webトレンドを先取りできるよう、この記事をお役立て下さい。
パンタグラフでは、トレンドや新技術を取り入れたWebマーケティング、コンテンツSEOをはじめ、Webサービスに関するUI/UXコンサルティングや開発支援を行っております。
ご相談は無料で承っておりますので、以下のボタンよりお気軽にお問い合わせください。
関連する記事
pagetop